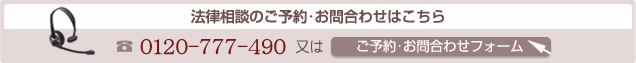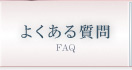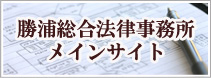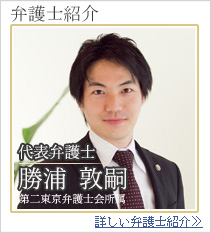トップページ > 為替デリバティブの問題点
為替デリバティブの問題点
為替デリバティブ取引の問題点は、大きく分けて、1.商品そのものの問題点、2.勧誘先の選定についての問題点、3.商品の説明についての問題点に分けられます。
1.商品そのものの問題点
まず、銀行が勧誘した為替デリバティブ取引は、その取引の内容自体に問題があるものです。典型的な為替デリバティブ取引は、簡単にいうと、例えば米ドルが基準レートよりもドル高になった場合に顧客が得をする代わりに、基準価格よりも円高になった場合には顧客が損をするという取引です。
この際、企業側が銀行に支払う手数料をなくしたり、基準レートを有利な水準に見せるために、企業のリスクを増大させる特約が付されることになります。銀行側の損失にだけ上限をつけるノックアウト条項、ドル高時の利益に比べ、円高時の損失を倍増させるレシオ特約などと言われるものです。
このように為替デリバティブ取引は、金融商品として非常に複雑なものであるうえ、長期間にわたって企業を拘束し、その健全な財務体質を害する危険な取引なのです。
2.勧誘先の選定についての問題点
為替デリバティブ取引は、本来、企業にとってのリスクを軽減する手段のはずであり、企業経営に不必要なリスクを新しく生じさせるような為替デリバティブ取引は許容されるべきではありません。
一般的に、「金融機関が顧客に金融取引を勧誘する場合、顧客の投資に関する知識・経験・財産の状況、金融取引の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならない」というルールがあります(適合性の原則)。
当然ながら為替デリバティブ取引についてもこの原則があてはまりますので、御社にとって不必要なデリバティブ取引や、御社の事業規模に照らして過大なデリバティブ取引を勧誘した金融機関は、この原則に違反したことになるのです。例えば、ドル建ての支払を必要としない企業に対し、ドル高のリスクに対処するための商品を勧誘することは、顧客の金融取引の目的に照らして不適当というべきでしょう。しかしながら、実際には、為替リスクを負わないような企業にも、為替デリバティブ取引の勧誘がなされていたのです。
3.商品の説明についての問題点
1に記載したとおり、為替デリバティブ取引は、非常に複雑な取引です。御社は金融機関ではないので、金融取引の専門的知識を有するわけではありません。他方、金融機関は複雑な(そして危険な)商品を勧誘する以上、その商品の特性やリスクについて十分な説明を行う必要があります。
しかしながら、実態として、為替デリバティブ取引の勧誘の際に、顧客に十分な説明がなされていないケースが数多く存在します。そもそも金融機関の担当者自身が、為替デリバティブ取引について十分に理解しないまま勧誘を行ったという理由と、金融機関としては多くの顧客に為替デリバティブを売りつけることで収益を上げたいという意向があったという二つの理由によるものだと考えられます。